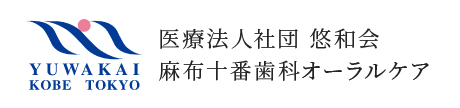歯の変色について

こんにちは、麻布十番歯科オーラルケアです。
寒い冬が終わり桜の季節が訪れたなと思っていたところ、日々の気温がどんどん上昇し,気づけば桜は散り、少し汗ばむ初夏のような天候となりました。
今回のお話は歯の変色についてです。
変色といっても様々な原因があります。
例えば先天性の原因はテトラサイクリンという薬剤による変色など
後天性の原因は飲食物による着色や神経が死んでしまうことによるもの(以下失活歯)などが挙げられます。
先天性の変色の場合、多くはホワイトニングによって改善が期待されます。
ホワイトニングの種類に関してはhttps://www.azabujuban-oralcare.jp/blog/post-14/の記事を、また当院のホワイトニングに関してはhttps://www.azabujuban-oralcare.jp/blog/post-30/の記事をご覧ください。
後天性の変色の場合、飲食物による着色はクリーニングでしっかりと清掃すれば改善します。当院では保険診療内でプロフィーという機械を用いて、着色含めてバイオフィルムも落としますので、健康的な口腔内環境をご提供できると思います。
では失活歯の変色への対応は何ができるでしょうか。
当院では以下の3つの方法をご提案できます。
1)ウォーキングブリーチ
2)ダイレクトボンディングによるベニヤ修復
3)被せ物によるオールセラミック補綴
以下それぞれについて複数の投稿に分けて詳しく説明します。
今回はウォーキングブリーチについての説明です。
1)ウォーキングブリーチ
ご自身の天然の歯の大部分が残っている場合、歯の内部から漂白を行うことで白くする方法をウォーキングブリーチといいます。
転倒やスポーツ中の事故で強くぶつけたり、矯正中の過剰な力がかかったりし、歯の神経が死んでしまう事があります。多くは自覚なく時間を経て変色するため、歯の色が変わってきたことに気づいた際、患者さんご本人が原因に気づかず過ごされる事があります。
また虫歯で歯の神経を取らざるを得ず、根の治療を過去にした歯も長期経過後に変色の原因となります。
ご自身の歯が大部分残っており、表側の歯がしっかりと残っている場合、根の治療を行ったのち、ウォーキングブリーチを行います。おおよそ週1回の治療で2~3回の来院回数が必要です。治療期間中は舌側に小さな穴を空け、その穴に薬剤を入れた後、穴をふさぎます。
利点:ご自身の歯を残した上で色の改善を図れる
表面がご自身の歯の為、他の天然の歯と変わらない
他の変色改善の方法と比べて安価
欠点:根の治療を行う為、治療回数と期間がかかる
漂白の薬剤の影響で術後強い痛みがでる可能性がある
一時的な穴をふさぐ材料が取れやすい
上記の説明はいかがでしょうか。
お勧めされる方
・自身の天然の歯を極力削りたくない方
・唇側の天然の歯がしっかりと残っている方
・隣り合う歯が天然の歯の方
・歯の内部からの着色が原因の方
お勧めできない方
・被せ物になっている歯の変色が気になる方
・歯の大部分を詰め物で治療されている方
ご予約はお電話0352320146
またはweb予約https://www.shika-town.com/t00001315/reservation
からお待ちしております。
医療法人社団 悠和会 麻布十番歯科オーラルケア
〒106-0045 東京都港区麻布十番3-14-5 ローズビル1F
監修者 鳥居 秀平 医療法人社団 悠和会 北野坂鳥居歯科医院/理事長

「医は仁術」の理念に基づき、患者様の気持ちに寄り添い、誠実で愛情ある治療を行うことを大切にしています。当院では、患者様の不安や希望を伺い、その方に適した治療を提供することを重視しています。オペ室や歯科用CT、マイクロスコープなどの設備を整え、安全で信頼できる治療環境を整えており、スタッフ一同、患者様の大切な歯を守るために努めております。
略歴
- 1994年 日本大学松戸歯学部卒業
- 1996年 英国マンチェスター大学研究在籍
- 1998年 国立大学 東京科学大学大学 歯学部 文部教官
- 1998年 東京科学大学付属歯科衛生士学校 講師
- 1999年 国立大学法人 東京科学大学大学院医歯学総合研究科
顎顔面機能再建学系専攻 文部科学教官 - 2001年 北野坂鳥居歯科 開業
所属
- 日本口腔インプラント学会 専門医
- アジア口腔インプラント学会 認定医